こんにちは!朝山家の聡士(@HbHlUnRqYkjbRMQ)です。
大分県豊後大野市の緒方町の里山の集落から発信しています。
約1年半前からスタートした古民家リノベーション。
完成してからは、宿として生まれ変わり、3桁の人数も来客があり嬉しい限りです!
今回は、経験したことをもとにしてDIYで漆喰を塗る際に失敗しがちなことをこれから左官作業に挑戦する方に向けて書きたいと思います。
DIYで失敗しないためにも初心者は絶対に知っておいた方が良いと思います!

古民家は漆喰をおすすめする理由はこちらの記事をどうぞ!
関連記事:【DIY】壁紙NG?カビ対策に漆喰を塗ろう!湿気が多い里山の古民家の場合
それではいってみましょう!
【失敗01】漆喰を塗る前にシーラーを塗らない
漆喰を買ってきて、さあ塗ろう!では仕上がった後に失敗に気がつきます。時すでにおそし。
既存の壁からしみやアクが出てきたり漆喰を塗った直後は良いかもしれませんが、ボロっと剥がれてしまいます。構造用合板も漆喰を塗った際に茶色のシミのようなアクが浮き上がってきます。

写真:合板にシーラーを2度塗りしていなかったためアクが出てきた壁
シーラーを塗らないで直接漆喰を塗っても良いのは土壁の場合が多いと思います。
しかし、土壁の状態次第ではそれもNGです。
土がボロボロと落ちる際は、樹脂系のシーラーで完全にかためてしまう方法もあります。
しかし、古民家のリノベーションやリフォームの場合はそのまま既存の壁に塗るもしくは、壁の下地をやりかえて新しい石膏ボードにするはずです。
じゃあどんなシーラーを選べばいいのかおすすめのシーラーを紹介します。
まずはシーラーの役割から!
シーラーの役割は、主に4つ!
- 下地の調整(下地に漆喰の水分が奪われて急激に乾燥することを防ぐ)
- 漆喰の接着力の向上
- 既存の壁から浮き出てくるアクを防止する
- 塗装ムラがなくなり均一に塗ることができる
シーラーの種類はたくさんありますが、ホームセンターで購入すると広範囲を塗る際は大量に購入する必要があるためコストがかかります。
業務用の一斗缶に入ったものを購入することをおすすめします!
新しい石膏ボードにおすすめのシーラー
漆喰の特徴として強アルカリ性なので、石膏ボードには直接塗ることが出来ません!
必ずシーラーを塗りましょう!
ホームセンターに売っている一般的なシーラーはこちら。
初期のDIYの練習ではこちらを使っていました。あまり塗る範囲がなかったためです。
水性のカチオン系のシーラーの特徴としては、化学成分が少なく人体に影響が少ないこと。
古い繊維壁・砂壁・聚落壁などにおすすめのシーラー
おすすめは、ロハスウォールのシーラーです。
「ガードシーラー」は効果を発揮してもらうためにも2度塗りをしましょう!
DIYする壁の面積が広い場合は、18kgの一斗缶を購入するのがコスパが良いです。
構造用合板・ベニア・コンパネにおすすめのシーラー
一度のシーラー処理ではまずアクの浮き出しが防げないので2度塗りをしましょう!
筆者は一回で良いやろ!と思って塗ってしまいアクが浮き出て失敗しました、、、。
ロハスウォールのシーラーももちろん使えます。
近畿壁材さんの「島かべプライマー」がおすすめです。

ビニールクロス・紙クロス・布クロスにおすすめのシーラー
「フジワラ化学」のエマルション系下地処理剤の「アクドメール」がお勧め。
アクとシミを強力に止めてくれます。
しかも、下地の補強もできるので一石二鳥。
このシーラーの特徴は、特殊な骨材が入っているのでアク止め効果が強力です。

モルタル・コンクリートにおすすめのシーラー
関西ペイントさんの合成樹脂エマルションシーラー「EPシーラー透明」です!
この商品はとにかくコスパが良いです。コンクリート・モルタル・スレート・石こうボードに使えます。
「EPシーラーの白」は、使ってみた感想なのですが
外装などに使った方が良いと感じました。
手に付着するとなかなか取れないし、
内装作業をする際はきちんと養生をしないと大変なことになります。
落とすのがとにかく大変!
筆者は、作業中にこぼしてしまい大変なことになりました。2枚目の写真なんて最悪です。
この投稿をInstagramで見る
ペンキが塗られた壁におすすめのシーラー
ガードシーラーは効果を発揮してもらうためにも2度塗りをしましょう!
DIYする壁の面積が広い場合は、18kgの一斗缶を購入するのがコスパが良いです。
【失敗02】既存の古い壁下地が動く
塗ろうとしている壁、もしかして押したらブカブカ動きませんか?
動いてしまう場合は、一度解体して壁から作り直す必要があります。
これは、タイムロスですが仕上げをする以前の問題なので木材などの下地を作って石膏ボードを張りましょう。
漆喰をそのまま塗ってしまうと、割れてしまったりきれいに仕上がりません。

これでDIYで失敗したと言う声も結構聞きますし、実際に下地から作り直しました。
下地をしっかり作ることでクラックも発生せず綺麗に仕上げることができます。

特に古い中古住宅や古民家は、何度も何度もリフォームしていると何層も壁材が重なっていることも。
ある知り合いのDIYを手伝った際に壊してみると、土壁→漆喰→砂壁→漆喰→軽量モルタル →漆喰→聚落→漆喰のような地層のような状態の壁もありました笑
DIYのアドバイスや漆喰の左官作業を頼まれた際に、経年劣化で内部の木が腐っていたりして
下地からやり直さないといけないことも結構ありました。
ちなみに筆者はDIYのアドバイスやリノベーションを仕事で受けてすることもあります。
【関連記事:空き家、敷地の再生など田舎ぐらしの困りごとを解決!〜パラレルライフデザインの紹介〜】
【失敗03】石膏ボードにパテ塗りをしない

石膏ボードにシーラーだけ処理して漆喰を塗ると石膏ボードと石膏ボードのつなぎ目から縦にヒビが入ることがあります。それは、パテ塗りをしていないからです。
※下地紙を貼る方法もあります。
絶対にひび割れを起こさない漆喰壁はありませんが、
クラックを防ぐためにもビスを打ち込んだ場所と継ぎ目にはパテを塗って
ひび割れを防ぎましょう。

また、パテ塗りをする際に継ぎ目を補強する副資材である「ファイバーテープ」も活用するのもおすすめです!
下塗りと上塗りを兼用できる「吉野石膏のタイガーパテ」が安価でコスパが最強です。
塗った後のパテの痩せも少なく水を加えるだけで練ることができるので作業性もGOODです。
【失敗04】パテを塗ったあと表面を研磨しない

研磨をしなくてもパテ塗りをしたあと、シーラーを塗ってそのまま漆喰を塗ることができます。
なんだ!全然大丈夫じゃん!
と筆者は作業をしていたのですが、漆喰を塗る過程で削っていればよかったと後悔するのです。
なぜパテを塗ったあと研磨をしないといけないか?と言うと漆喰を仕上げで塗るときに、
出っ張ったパテの凹凸が邪魔をして綺麗に塗れないからです。
特に、まっ平に漆喰を塗るときなんて最悪です。
漆喰を厚く塗ってしまうと、ひび割れの可能性が高まるし、かといって薄く塗るとパテが見えてしまいます。
なので、横着せずしっかりと出っ張った硬化後のパテをサンドペーパーでヤスってからシーラー作業、漆喰作業をしてくださいね!
ちなみに、サンドペーパだけでも研磨することは可能ですが、高くないので治具を買って作業すると効率も作業性も上がって良いです!
Amazonで購入して使っています。おすすめです。
そしてこのやすり作業、パテを削って出る白い粉がかなり舞います。
窓を開けておくか、扇風機で排気しないと他の部屋が粉だらけになります。
【失敗05】漆喰がしっかり混ざっていない
はじめから練ってある漆喰を購入すれば均一に混ざっているので関係のないことですが、
粉漆喰から水を入れて練る方は、しっかりと混ぜると失敗の可能性を減らすことができます。
ちなみに、しっかりと混ざっていないとダマになってしまい漆喰を塗るときに混ぜる手間も時間もかかりますし、しっかりと塗ることができません。
筆者は予算がなかったので攪拌機を買わず、
インパクトドライバーの先にペイントミキサーをつけて少しずつ粉漆喰を攪拌しました。

これが失敗の始まり。
ペイントミキサーの先が壊れてしまうし、少量しか練り上げる事が出来ないのでかなり時間がかかります。
今になって攪拌機を最初から買えばよかったなと後悔しています。
レンタルする方法もあるので粉漆喰を練る際は文明の利器「攪拌機」を使って
ちなみに現在、DIYからレベルアップして左官仕事もたまにしています。
そこで使っている攪拌器はこちらです。
【失敗06】水の入れすぎで漆喰がゆるすぎる
漆喰が緩いなら、粉漆喰を足せばいいじゃん!と思うかもしれません。
しかし、ずっと作業していると集中力が切れてしまいついつい水を入れすぎてしまい、
ゆるゆるの漆喰ができてしまうことも。
これをそのまま使ってしまうとどうなるかと言うとテッカテカの仕上がりになります笑
漆喰なのに表面がテカテカに。
しかも、左官こてに乗らないし作業性は最悪です。
温度や湿度によっても練り具合が変わるので、練った漆喰の様子を見ながら調整することが大切です。
【失敗07】壁の隅から塗らない

これは、漆喰作業をやっていく中で気がついたのですが
丁寧に作業する箇所(集中が必要な場所)から先に仕上げていくことが失敗しないコツだと感じました。
壁の隅や(入隅や出隅)を先に塗ってしまえば、後は大きな面を大胆に塗るだけ!

【失敗08】マスキングテープなどで養生をしない
養生をせずに漆喰を塗ってしまった結果がこれです。

マスキングテープやマスカーテープを貼らずに作業すると絶対に綺麗に仕上がりません。
ちなみに、これはマスキングテープを貼ったけれども、漆喰を塗ったあとすぐに養生を外さなかったため漆喰が固まってしまい綺麗に仕上がりませんでした。

【失敗09】漆喰を厚く塗りすぎる
漆喰を薄く塗ってしまうと、下地が見えてしまい調湿効果、消臭効果など漆喰ならではの効果が薄れてしまいます。
逆に厚く塗ってしまうとなぜ失敗につながるかと言うと理由は2つあります。
- 見積もりの壁の広さ以上の漆喰を消費してしまいコストがかさむ
- 仕上がる過程で漆喰に含まれている水分の蒸発ムラができて割れにつながる

初心者で厚みを均一にコントロールするのは難しい。
【失敗10】漆喰を混ぜて寝かせずすぐ塗ってしまう
これは、粉漆喰の場合で失敗と言うか一手間かけるといった方が良いかもしれません。
DIYではあまりしないのかな?
とも思いますが、失敗のリスクを低くするためにもやって損はないです。
粉漆喰を水で練り上げた後、一晩おくことで塊や玉にならず、漆喰と水が馴染んで均一に混ざります。
【失敗11】一気に漆喰を塗らず境目を作ってしまう

これは、今の「朝山家」の談話室ができる前の写真です。
DIYで塗った際は、漆喰を塗る範囲がかなり広かったです。
よく、漆喰塗りのワークショップなど大人数で作業するかと言うと
漆喰は壁一面一気に塗り上げないといけないからです!
乾いた後の漆喰の上に漆喰を塗ると剥がれてきたり、
境目が綺麗に仕上がらなかったりするためです。
スケジュールと作業段取りをしっかりと把握した上で、一気に塗り上げましょう!

【失敗12】下地処理をせず漆喰の上に漆喰を塗ってしまう
同じ素材だから重ね塗りしても大丈夫でしょ!と思ったあなた。
それは間違い!筆者も最初思ったのですが、絶対やめて置いた方が良いです。
理由は、漆喰が乾いたあとペリペリっと剥がれてしまうからです。
塗り替え用の専用下地材を使いましょう。
塗らないで作業すると、写真のように剥がれて失敗します。
DIY初期の失敗の様子↓

あとは、気泡のようなぷくぷくとした凹凸ができてしまうこと。

せっかく塗ったのに剥がしてまた塗り直すなんてめんどくさいですよね?
そんな時は、漆喰の上に漆喰をぬる時の下地の処理をしましょう!
※あくまで下地の漆喰が傷んでいたり劣化していない状態が条件です。
漆喰の上に漆喰を塗るには、塗り替え用の専用下地材を塗るだけです。
漆喰の上に漆喰を塗る方法についてはロハスウォールの動画が参考になりますよ!
【失敗13】手袋をせずに素手で作業してしまう
これは、作業上の注意です!
漆喰自体はアルカリ性で手が荒れてしまうことがあります。
ゴム手袋をして作業することをおすすめします。また、粉漆喰を練る場合は目に粉塵が入らないようにゴーグルもつけましょう。目に入ったことがあるのですが、めちゃくちゃ痛かったです。
できる限りマスクもしておいた方が絶対良いです。
マスクは、防塵のものを。
ゴム手袋は厚手のものを。
ゴーグルは草刈をするときに使うものでもOK。

まとめ
いかがだったでしょうか?
DIYで漆喰を塗る際の失敗しないように注意することを紹介しました。
作業のイメージはついたでしょうか?
漆喰を塗る際に失敗を先に知っておけば、上手な漆喰壁に仕上がる可能性も高くなります!
失敗から学んで、できるだけたくさんの作業をこなすことで漆喰の左官作業は上達します。
この記事を読んだ方の漆喰作業や古民家再生、リノベーションがうまくいきますように願ってここまでにしたいと思います。ではまた!
関連記事▶︎【DIYレビュー】マキタ充電式オートパックスクリュードライバ FR451Dを使ってみた感想
関連記事▶︎【DIY】古民家改装中に床下から出てきたものとは?
(2022/11/18)
\筆者が実際に使っているDIY工具たちはこちら!/

\あさやけ編集部はTwitterもやってます!/ https://twitter.com/HbHlUnRqYkjbRMQ 
【こちらの記事もあわせてどうぞ!】






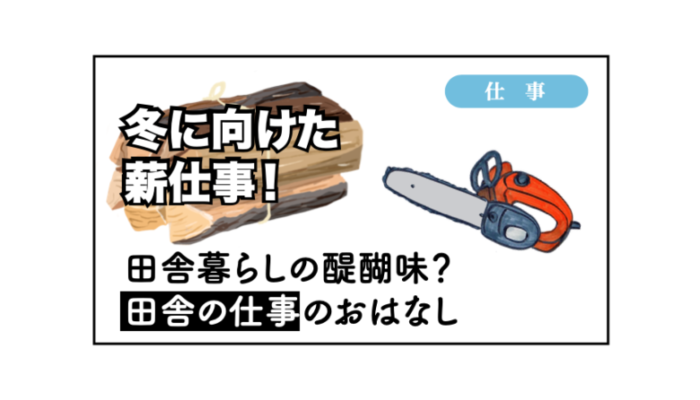







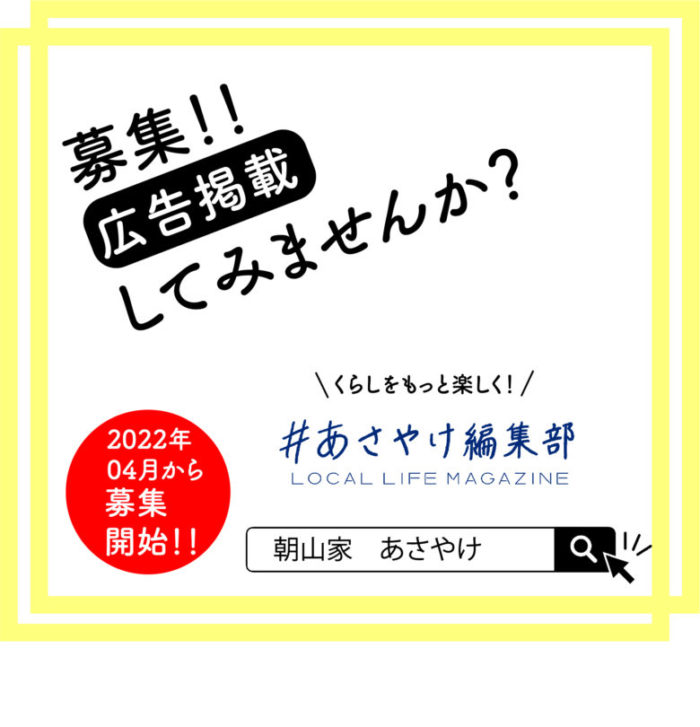

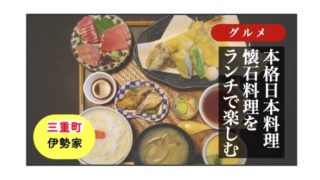
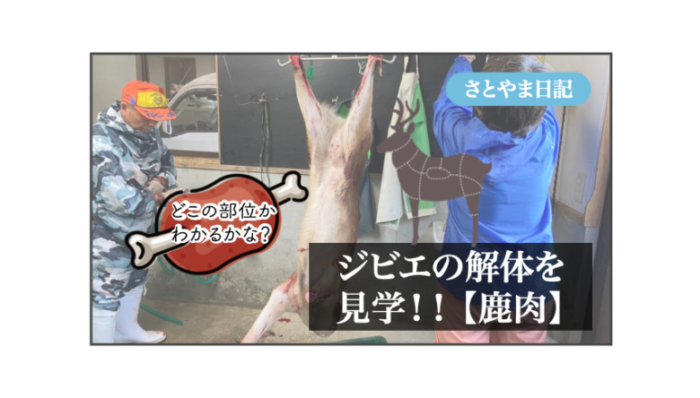
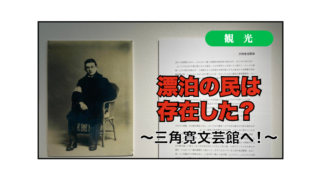






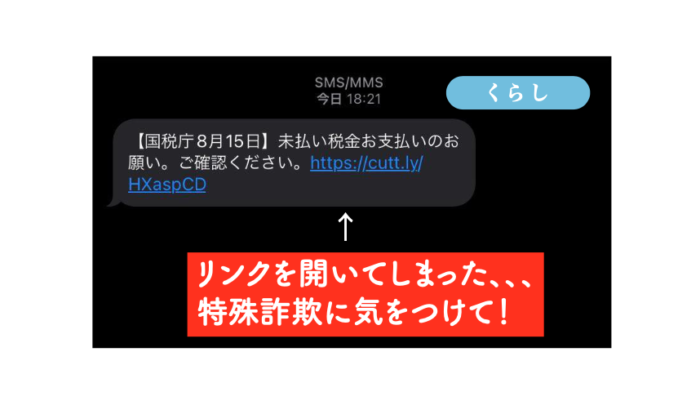


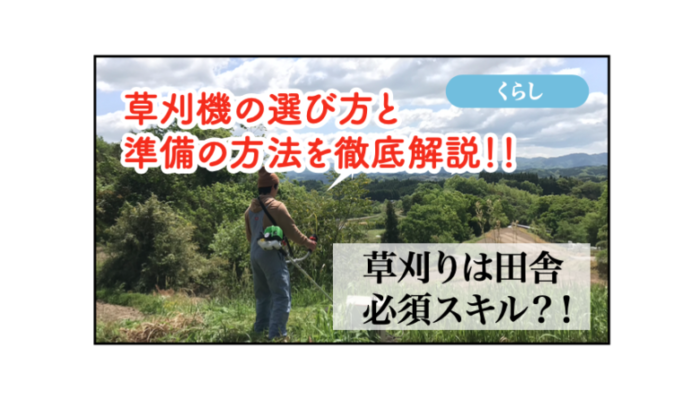



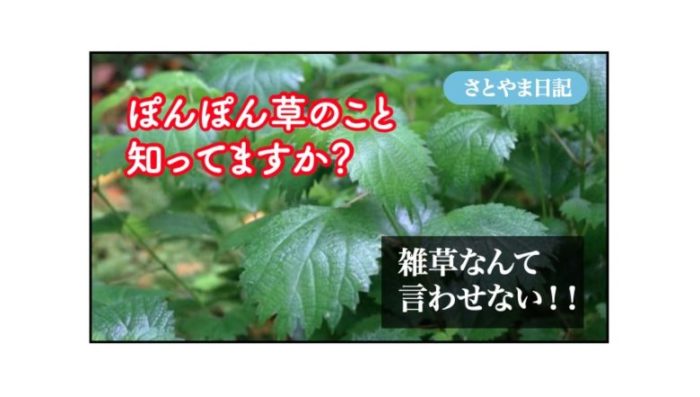

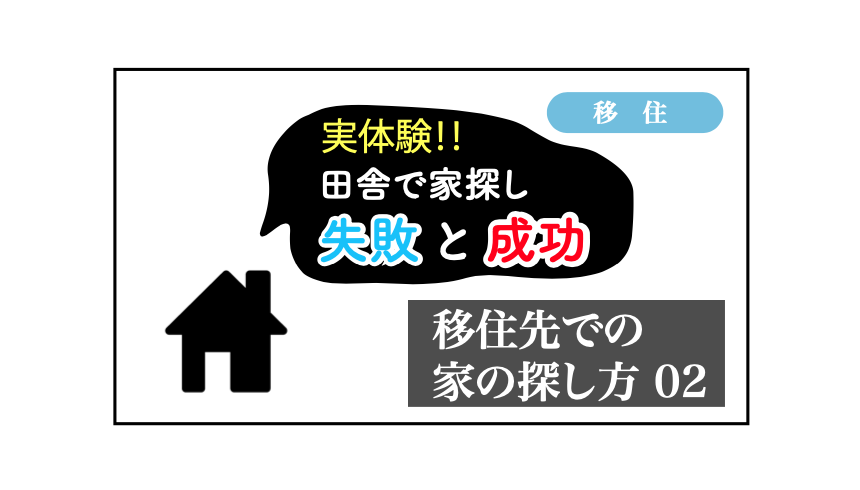



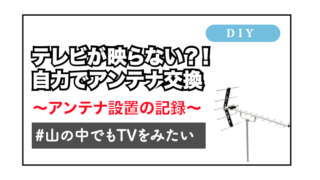
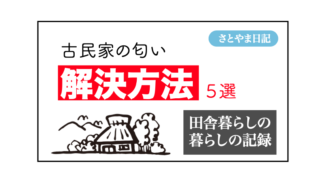


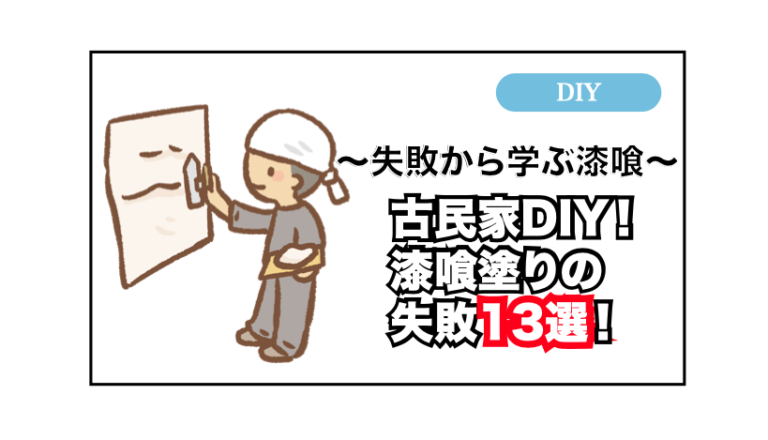






















カテゴリー