こんにちは!朝山家の聡士(@HbHlUnRqYkj?bRMQ)です。
大分県豊後大野市の緒方町の里山の集落から発信しています。
筆者は、空き家をDIYして再生し宿泊施設として活用しています。
DIYの際に床を解体した当時のことをふりかえって備忘録として記録したいと思います。

今回は、古民家を改装していた時のエピソード「床下から出てきたもの」です。
【関連記事:【DIY】古民家の床下に潜る。人生初の自分で床下点検!】
よく、古民家DIYのYouTube動画とかで出てくるアレですアレ。
なにが出てくるか気になりますよね?
時にはお宝が出てきたり、ゴミが出てきたり。
昔の生活を感じさせる古道具とか、へそくりが隠されていたらテンション上がります!
しかし!
この記事では、残念ながらそんな面白い展開はありません。
虫などの話が出てくるので、お食事中の方はお控えください笑
あくまでも空き家を改修した記録としての備忘録なのであしからず。
ただ、これから古民家を改装したりしてDIYする方にとっては
へ〜という情報かもしれないのでしばしお付き合いください。
関連記事▶︎【DIY】古民家や中古物件のおばあちゃんの家の匂いを消す方法
関連記事▶︎【DIY】「朝山家」が2年間空き家で廃墟だった頃。再生前のキッチンの様子。
それではいってみましょう。
床下から出てきたもの6つ!
DIYをする中で、
和室2部屋、事務室の3部屋を解体し新たに床を貼り直しました。
点検をした際には、気がつかなかったものに出会いました。
これらは、床下点検をした際には気がつかなかったものです。
関連記事▶︎【DIY】古民家の床下に潜る。人生初の自分で床下点検!
床下から出てきたもの【01】寛永通宝
まずはこれ!
この投稿をInstagramで見る
最初発見した際は、なんかの部品かな?
と思ったのですが、どうやら文字が書いてあり昔の硬貨っぽいぞ。
そこで、google先生に「昔のお金」、「日本」というサジェストで検索してみると
三菱UFJ銀行の貨幣史年表~日本の貨幣 そのあゆみ~というページがヒット。
発見した硬貨の文字を見る限り「寛永通寳」と書いてあり、
どうやら江戸時代に作られた銅で作られたお金のようです。
1624年から1644年までの期間が寛永(かんえい)という元号。
江戸時代から幕末にかけて製造されたものらしいけれど
いったいどのくらいぶりに、床下から日の目を浴びたのだろう?
寛永通寳はどのくらいの価値が着くのかというとピンキリのようですが、
記念に保管することにしました。
このお金を落としちゃった方!!無事に拾いましたよー!
床下から出てきたもの【02】昔のカンザシ(くし)
最初これを見つけた時にドキッとしました。
なんで床下に?!と思ったのですが、
畳を剥がして床板を確認した時に理由がわかりました。
床板の松板は、今のようにぴったり製材したような木材ではありませんでした。
つまり!木材と木材のつなぎ目に隙間があり畳の隙間に落ちてしまった薄いクシは
そのまま床板の隙間を通って床下に落ちてしまったという予想です。

昔の日本の風習として冠婚葬祭は、戸主の家で行うことが多かった日本。
このカンザシ(クシ)は元大家さんの持ち物だったのかもしれません。
もしそうだったとしたら元大家さんの70年前の結婚式のもの。
改修をスタートした際に出てきた今は亡き元大家さんの結婚当時の白黒写真を持って行ったことを思い出し、
これもお返ししたかったなとなんだか切なくなりました。
床下から出てきたもの【03】木屑など小さなごみ
古い木屑やプラスチックの何かの破片などが落ちていました。
元大家さんのおばあちゃんからは、
「何度か家のリフォームや床の張り替えなどメンテナンスをしていた」
という話を古民家を購入する前に聞いていました。
その際に作業した大工さんが残していったものでしょう。
現場の職人さんの意識にもよりますが、気が回らなかったのでしょうね。
綺麗な仕事をしたとしても、後片付けはしっかりしていって欲しいものです。
床下から出てきたもの【04】古い水道管
床下に長い錆びた棒状の管が不自然な場所にあって、
これなんだろう?
と水配管を確認してみると普通に水道管も配管も繋がっています。
床下に入りづらい箇所にあることをみると、
これもリフォームの跡か!と気がつきました。
水道管を変える際に、古い水道管をそのまま残して行ったのでしょうね。
ちなみにこの古い水道管については、床下でグラインダーを使って切断する作業は危険だと感じ、
そのままにしておくことにしました。
床下から出てきたもの【05】蛇の抜け殻
床下に蛇が住んでいたなんて、現在の高気密な一般住宅では考えられませんね!
古民家の床下は布基礎(土の基礎)で、床下換気口として穴の開いたブロックが数カ所あります。
なので、風がよく通って床下に湿気がたまらず良いのです。
ですが、空気以外にも小動物まで入れてしまう。
それを狙って蛇が住み着いていたのでしょうね。
蛇の抜け殻がたくさんあるということは、ずっとそこに住んでいたのかなと思いました。
しかし蛇が床下に住んでいることは決して悪いことではありません。
昔から蛇の住む家は幸運が訪れ、お金もちになるという言い伝えがあります。
どうか逃げないで住み続けてくれ!と祈ったのでした。
床下から出てきたもの【06】お亡くなりになった虫など
※写真は載せないことにしました。
床下に点々と様々な虫の死骸が落ちていたのですが、虫よりも風通しが大切です。
木を食べてしまうシロアリは乾燥に弱く、シロアリの入った跡を蟻道と言うのですがそれもなく安心。
ダンゴムシ、ゾウリムシもいたのですが通気口が開いている以上仕方ない。
乾燥してカラカラになっているムカデの死骸やヤスデの死骸がありました。
※写真は載せないことにしました。
一番気持ち悪かったのは、ゲジゲジとゴキブリの卵でした。
それと同時に、ゴキブリを捕食してくれるアシダカグモさんの抜け殻があって食物連鎖が床下にもなるんだなと変に感心しました。
殺虫剤など化学的なものは、昆虫すら死んでしまうなら人間にも絶対よくないと思うので
土間ほうきで綺麗にそれらの侵入者を除去して終了。
床下の環境を良くすることは家を長持ちさせるために大切なこと。
年に一回は点検したいと思います。
まとめ
床下の風通しもよく、通気を妨げる障害物はありませんでした。
障害物などがあると、通気口からの空気の通り道も塞いでしまい換気が悪くなってしまいます。
そして、虫の死骸があったものの意外と床下は綺麗な状態で安心しました。
また、動物の死骸などもなく安心しました。
床下の状態が悪いと、家の健康寿命が短くなることにもつながるので
今後も定期的にチェックしていきたいと思います。
(2023/03/22)
\筆者のおすすめはこちら!/
【こちらの記事も読まれています!】

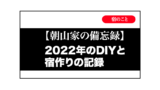



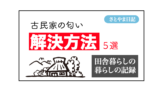



\あさやけ編集部はTwitterもやってます!/





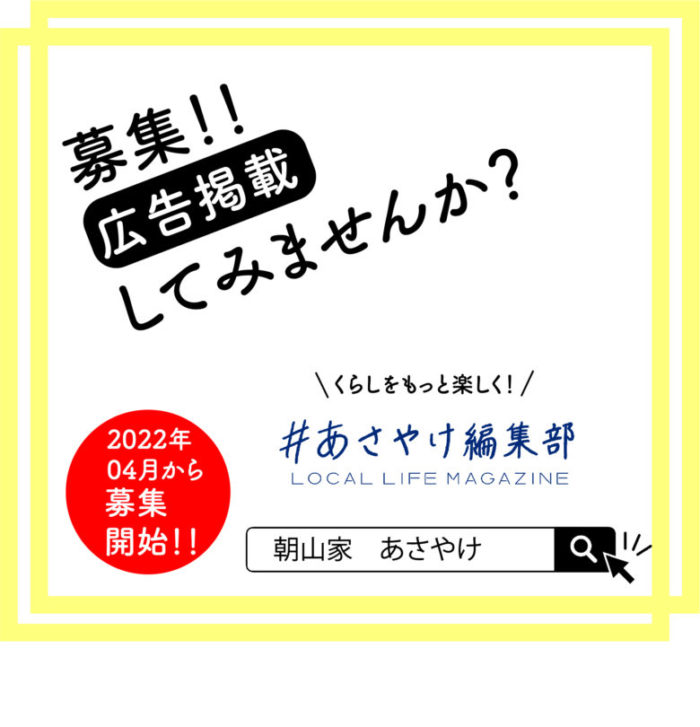
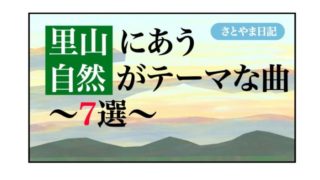
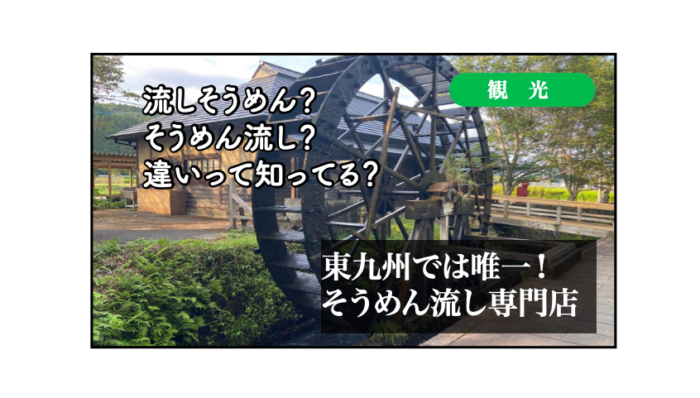




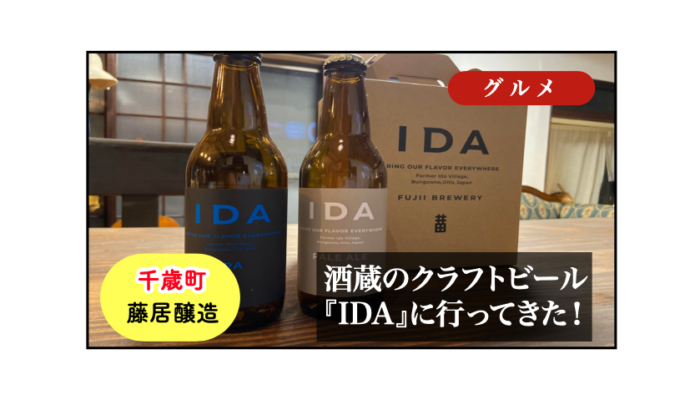

















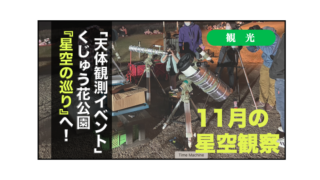


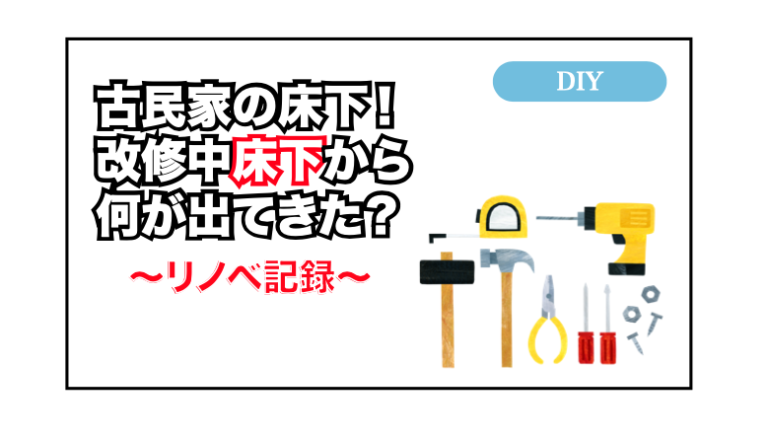
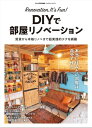
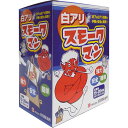



カテゴリー