こんにちは!朝山家の聡士(@HbHlUnRqYkjbRMQ)です。
大分県豊後大野市の緒方町の里山の集落から発信しています。
今回は、農業用の水路に倒れかかってしまった倒木を片付けるまでのお話です。
普通の支障木の撤去と違うのは
“元水源地だった場所に生えていた御神木”と”傾斜地からの倒木”
ということ。
それではいってみましょう!
倒木に気がついたきっかけ
朝山家がある場所の下には棚田が広がっていますが、中には残念なことに耕作放置になってしまった場所もあります。
移住してきた時には生えていなかったはずの竹がボウボウに生い茂ってきており、景観も悪いし
なんとかならないのかなと近くの農家さんと一緒に行ってみると
あれ?!木が倒れてる?!しかも農業用の水路へ?!

水路は誰のもの?
ここの地域では水路の財産管理・機能管理は富士緒井路という土地改良区が管理していますが
倒木の場合、その土地の管理は所有者の責任になり自分たちでなんとかしなければなりません。
なんてこった。それはそうだよな…。

富士緒井路土地改良区 白山ダム
土地の持ち主が片付ける?
倒木のあった場所の登記上の地目は池沼だと地域の方は言います。
残念ながら土地の持ち主は故人であり、お願いすることもできません。

むかしは、集落の方々が共同で使っていた水源だったようですが
湧水が枯れてしまったため、神官さんを呼んで水源地じまい?をしたようです。
土地の持ち主は個人の持ち物ですが、共同で使用していたという意識が集落の皆さんに
根強く残っていたこともあって、みんなで片付けようという意識につながりました。
水神様に御神酒(おみき)を備える
作業をする前に御神木に御神酒をかけ、作業をする私たちも少し口に含みます。
安全祈願の目的もあるようです。

木にお供えするだけかと思っていたので、最初は作業前に飲んだら危ないじゃないかと
思いましたが、それはしきたりのようです。
草刈機で周辺の下刈りをする
御神酒を供えたあとは、周辺の作業環境の整備に入っていきます。
作業性を上げるためと足場を安定させるために草刈機を使って、周辺の草などを片付けます。

チェーンソーで枝を落とす
写真ではわかりづらいですが、倒木を引き上げる上で邪魔な木を切っていきます。
作業しているのは86歳のベテラン山師。傾斜地なのにテキパキ動けてすごい。脱帽です。
倒木の他にも支障木もありました。支障木を倒すのは、素人には厳しいのでベテラン山師の方が
先陣を切って作業されていました。

倒れる方向をコントロールする
「チルホール」 という機械でワイヤーを張りながら、木の倒れる方向をコントロールします。
専用のワイヤーをチルホールの中に通し、レバーを往復させることで木などの重量物を引っ張ることが出来る、
ハンドウインチです。

最初はチル!チル!といいながらレバーを笑顔でひいているので、
“チルってる”っていう若者の流行語を80代も知っているのかな。合わせてくれてる感が優しいなと
思っていましたが、無知とは怖いものです。そんな生やさしい世界ではありませんでした。
一歩間違えれば命に関わることです。ふざけるのはご法度。
重機で倒木を引き上げる
まずはショベルカーの先端にワイヤーを通してシャックルという金物で固定します。
片方のワイヤーを倒木にくくりつけて引き上げていきます。

隣人は重機を使える方。田舎の人はなんでもできる。すごい!
短くコマ切りする
やっとわたしができる作業が回ってきました。
使用しているのは、薪割りで使うMAKITAのMEA3201Mという機種。有効切断長平均25~40cm程度です。
巨木には太刀打ちできないので、片付けをしやすいように小さく切っていきます。

山師の師匠が使っているチェーンソーの数はなんと6台!
『竹など、伐木する対象や、使用する木の直径で使い分けるんじゃ。』
とニコニコしながらおっしゃっていました。

道具の扱いで怒られる
作業中にチェーンが緩んでいることに気がつかずに作業していました。
『チェーンを締めないと道具がダメになるよ!』
ただでさえ重労働をしているのに周りが見えているのはやはりベテラン。

チェーンソーの刃の目とぎ講習もしてくださりました。ためになる。ありがたい…。
まとめ
中山間地域で農業を営むということは、作物を作るだけが仕事ではないことに大変さを感じました。
厳しい自然環境の中で何十年も暮らしや営みを続けてきた集落の方々。
みんなで助け合うことの大切さは地域ぐるみで生活を守るたくましさにつながっていると実感しました。
(2022/02/27の出来事)
【こちらの記事も合わせてどうぞ!】

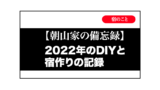






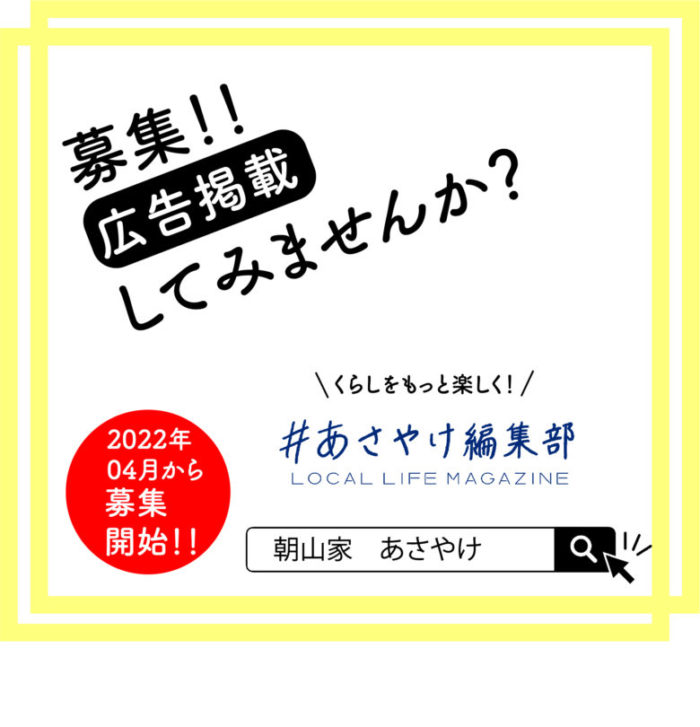
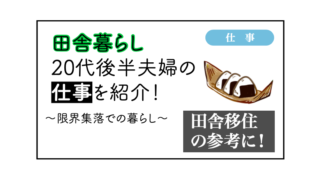

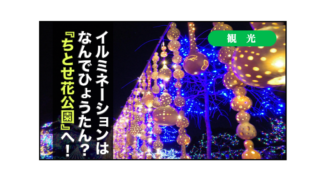

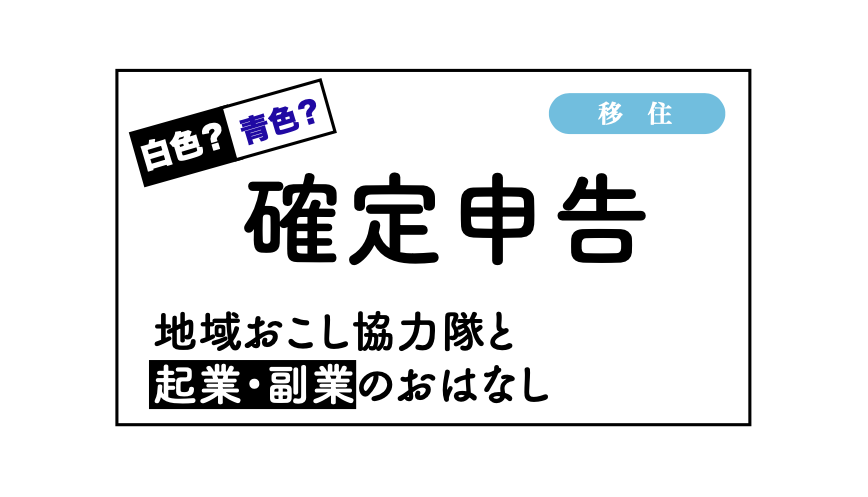
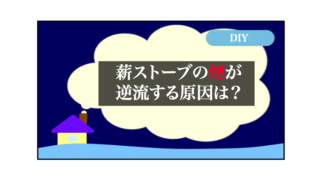


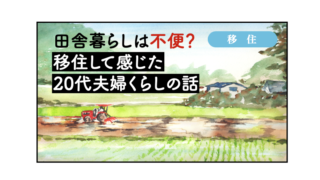
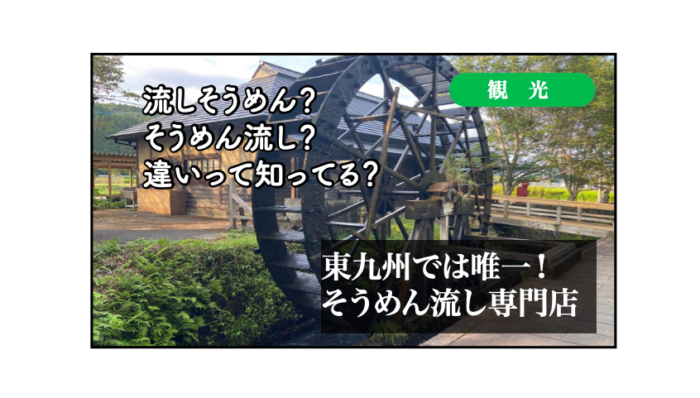




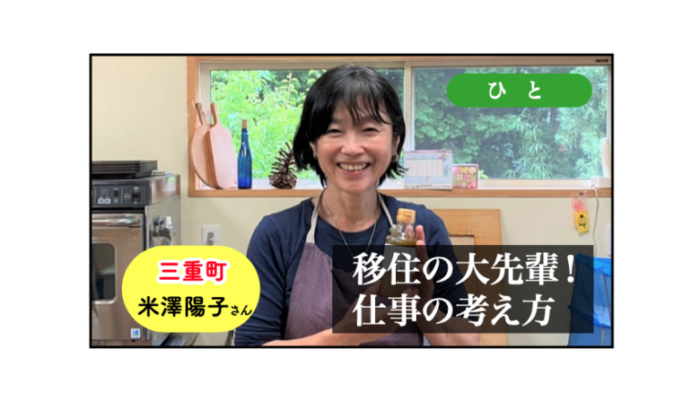







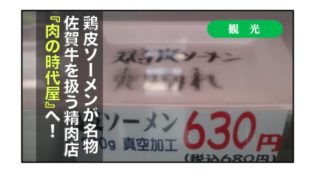

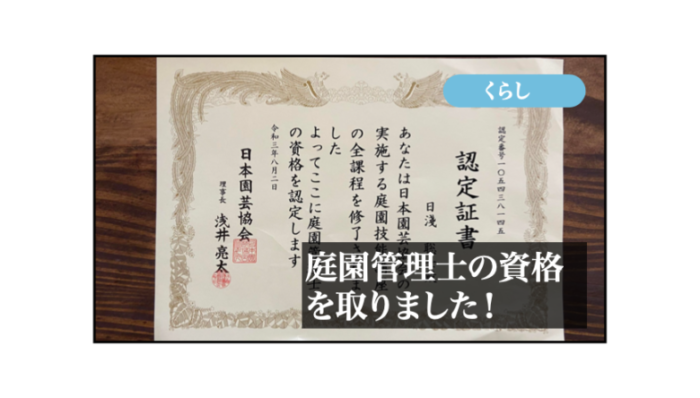






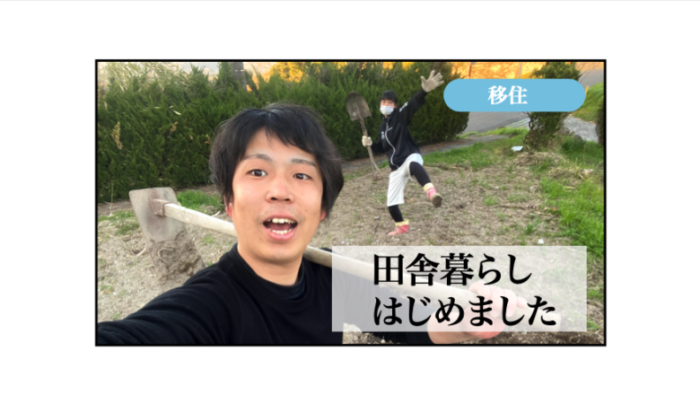

カテゴリー