こんにちは!朝山家の聡士(@HbHlUnRqYkjbRMQ)です。
私たちが住む大分県豊後大野市の限界集落から発信しています。
里山もだんだんと気温も上がってきて、日中は砂漠か!と言いたくなる暑さです。
夕方になってくると、標高が少し高いので暑さが和らいで過ごしやすくなります。
さてさて、今回の記事はスズメバチトラップをDIYで設置して
その後1ヶ月、どうなったか?と言う内容です。
DIYでのスズメバチ トラップの作り方はこちらをどうぞ。

1ヶ月後のトラップの様子
日中、巣作りの場所やエサを探しにスズメバチは飛び回っています。
トラップを設置している場所に、スズメバチがもし引き寄せられていた場合、
刺されてしまうことを避けるため、日が落ちてから確認しました。
誘引液は半分以下になっていました。
トラップの表面には白い膜のようなものができていて、
正直触りたくない状態。
お食事中の方のために、モザイクをかけておきました。

スズメバチトラップに蜂はかかった?
1ヶ月間様子を見ましたが、
残念ながらスズメバチは入っていませんでした。
家の付近でもスズメバチを見かけたこともなく、
どこか別の場所に行ってしまったのかなとほっとしました。
ちなみに、少し離れた集落の方は、外作業時にスズメバチに刺されてしまい
病院にて点滴を打つことになってしまったそうです。
外での作業時は気をつけたいものです。
ハチ以外のトラップにかかっていた虫
スズメバチ以外に、トラップに引っかかっていた昆虫を紹介します。
掛かっていた虫の大きさ順で、紹介していきたいと思います。
※虫が苦手な方は閲覧注意です。
トラップに入っていた虫01「ジャノメチョウ」
一番大きかった昆虫は、「ジャノメチョウ」と言う蝶々の仲間でした。
名前の通り、羽に蛇の目が描かれているような目玉模様が特徴の昆虫です。
最初、気持ちの悪い蛾が引っかかってるなと思ったのですが、蝶でした。
この模様、ちょっと怖いですよね。

眼状紋と言って、フクロウやヘビの眼に似た模様によって、
天敵である、鳥類等をびっくりさせるためという説があるらしいです。
鳥類ではなく、人間にやられてしまったと言うおちになりました。
トラップに入っていた虫02「ギンバエ」
お次は、ハエの仲間の「ギンバエ」です。
ハエじゃなかったら、美しい色をしているからうざがられなかったのに悲しいものです。
同じ色味のタマムシと比較すると、地位も残念ながら下位。
衛生的に良くない昆虫が数匹入っていました。

トラップに入っていた虫03「ミバエ」
ミバエっていう昆虫を初めて聞く方もいるかもしれません。
ミバエの見栄え!なんて親父ギャグを言う陽気な方もいらっしゃるかもしれませんが、
残念ながら、陽気な気分になれない昆虫です。
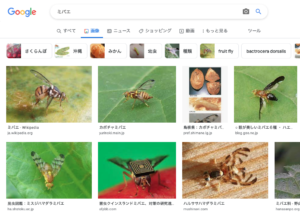
漢字で書くと「果実蠅」と書き、食品害虫です。
ミバエの成虫は果実内部に産卵するので、日本の農業に大きな被害を与える
植物検疫上重要な害虫として、警戒されています。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門
スズメバチトラップを作る際に、果実の皮などを入れたのが
この昆虫を誘引した理由でした。
トラップに入っていた虫04「アブ」
小さいハチのようなアブが数匹かかっていました。
見た目はハチのような、アブのようなハエのような昆虫。
とりあえず、判別が難しかったため、アブということにしました。
キャンプや川釣りなど夏のレジャー時に吸血されるやな虫です。

※血を吸わないタイプの草食系のやつも中にはいます。
では、アブとハエはどうやって見分けるか?
答えは、さなぎから成虫に羽化する過程で、
さなぎの裂け方が違うことで区別されるそう。
つまり、外見上の区別はできません!笑
まとめ
残念ながら、スズメバチがかかることはありませんでしたが
トラップを通じて、昆虫観察ができる形になりました。
身近にいる昆虫の生態を調べて見ると面白い発見があったりして、
暇つぶしぐらいにはなるかもしれませんね!
どうせトラップをかけるなら、カブト虫やクワガタ虫などを
とりたいと思うところです。
(2022/07/26)
【こちらの記事もあわせてどうぞ!】







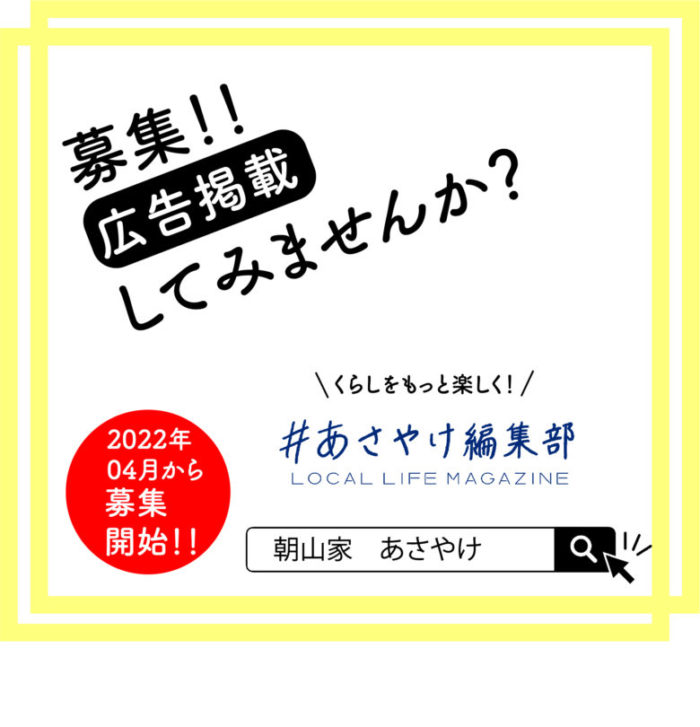
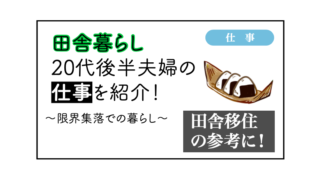







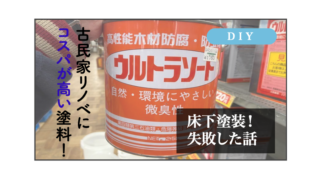



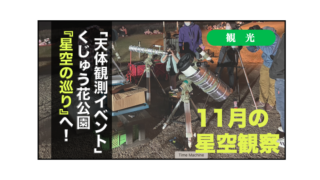




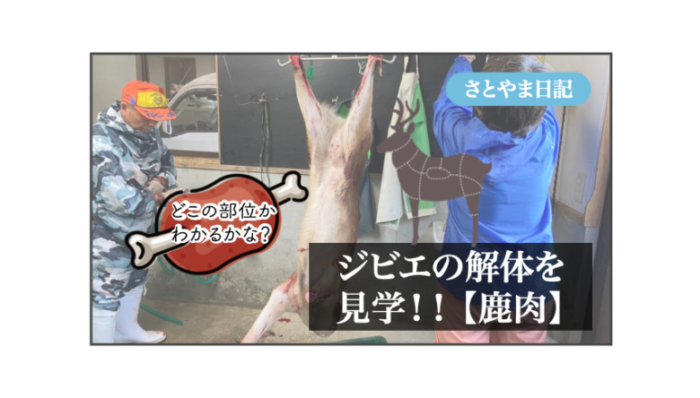
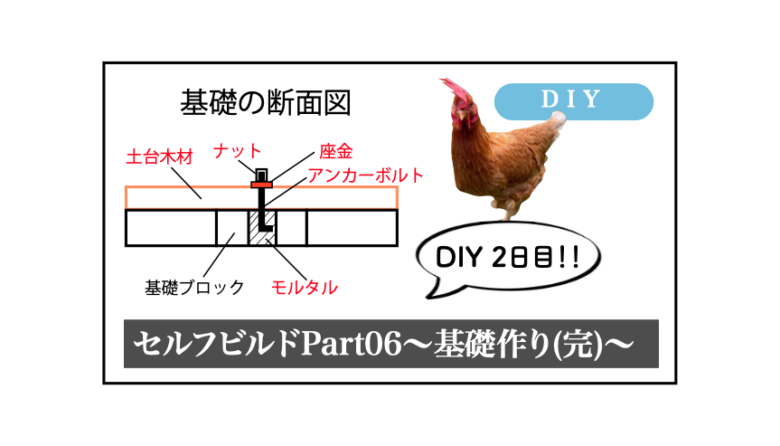



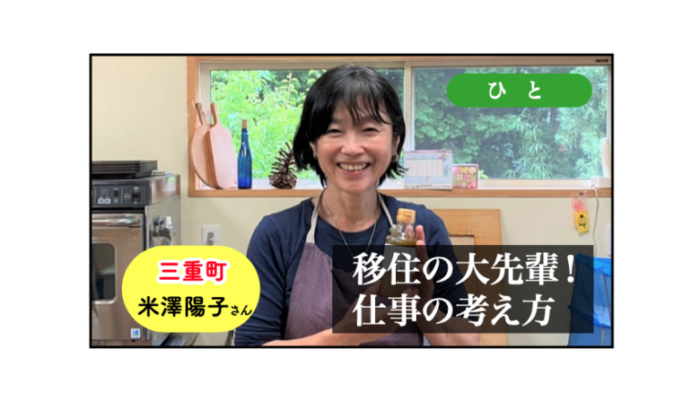

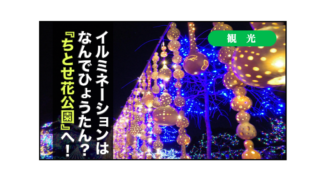


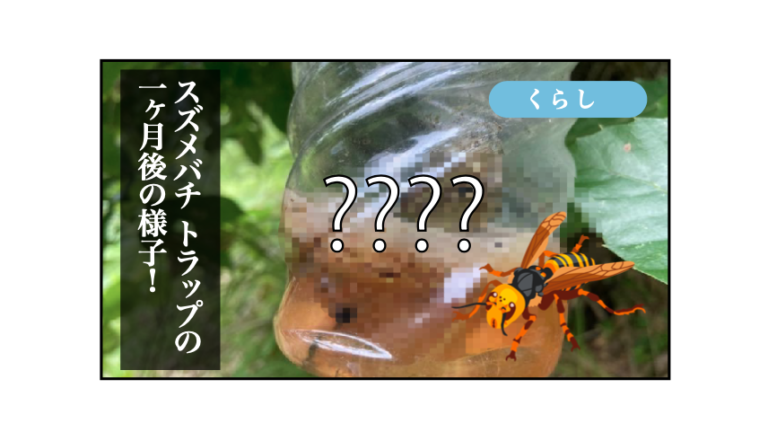




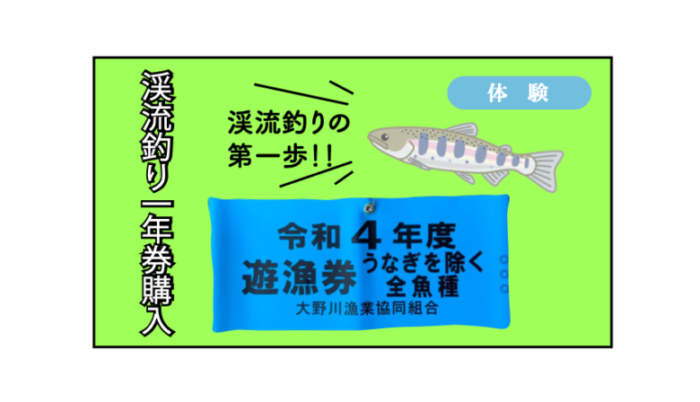

カテゴリー